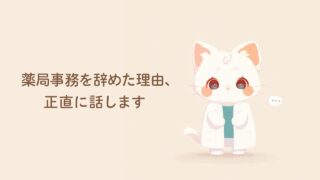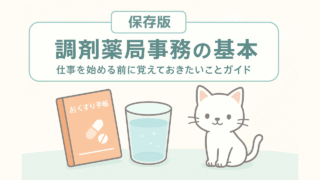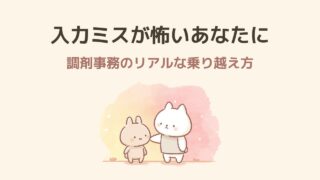医療しごとデビュー前に知っておきたい!やさしい基礎用語10選
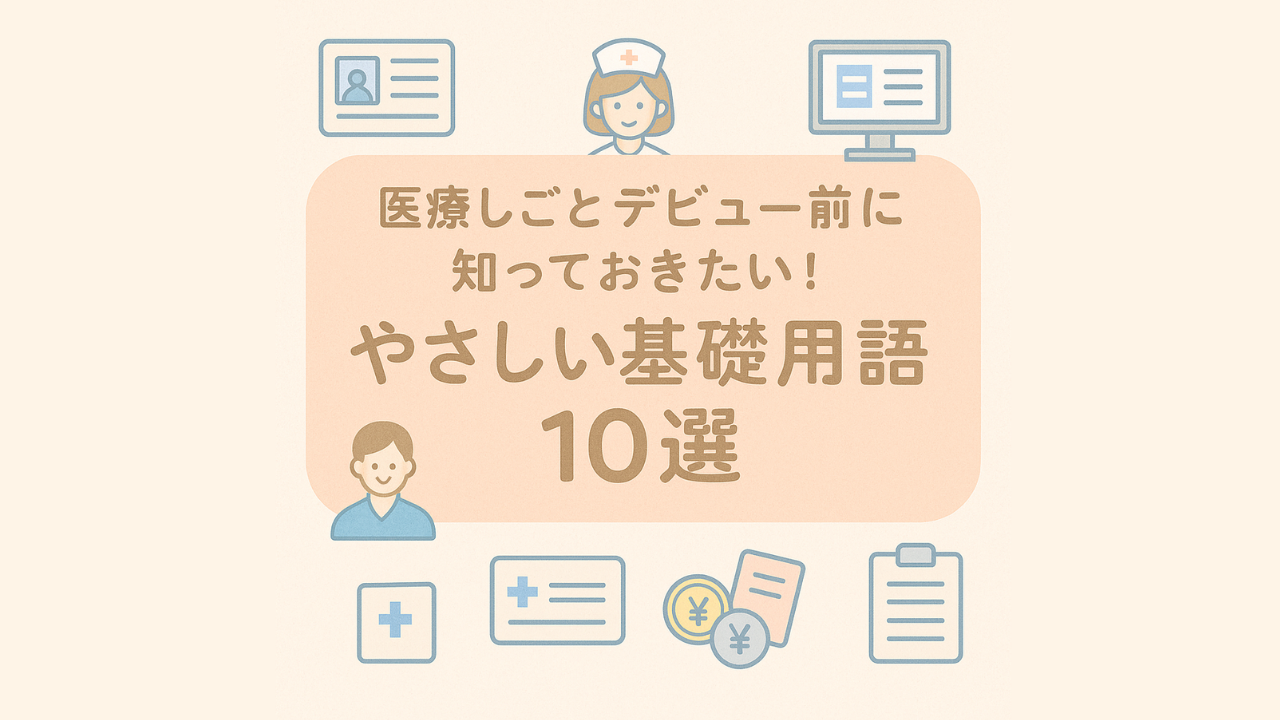
医療の仕事に興味があるけれど、専門用語が多くて不安…そんな方も多いのではないでしょうか?
この記事では、これから医療事務やクラークなどの医療現場で働きたい人向けに、よく使われる用語を10個にしぼって、やさしく解説していきます。
実際に働くときに「聞いたことある!」というだけでも安心感が違いますよ。
この記事でわかること
- 病院やクリニックでよく使われる用語の意味
- 実際にどんな場面で使われるのか
- 初心者にもわかりやすいイメージつきの説明
初学者向けの基礎用語10選
保険証(ほけんしょう)
患者さんが病院にかかるときに受付で提示するカードです。日本では多くの人が健康保険に加入しており、その証明として保険証を使います。
受付スタッフやクラークは、月のはじめや初診時にこの保険証を確認し、コピーをとったり、有効期限をチェックしたりするのが基本業務のひとつです。
受付業務(うけつけぎょうむ)
来院した患者さんに最初に対応する仕事です。あいさつから始まり、保険証の確認、問診票の受け取り、診察順の案内まで行います。
「病院の顔」と言われるように、患者さんにとって最初に接する大切なポジションです。丁寧で明るい対応が求められます。
会計業務(かいけいぎょうむ)
診察が終わった患者さんに対して、お金の受け取りや領収書の発行をする業務です。おつりの準備や、保険適用かどうかの判断も必要になります。
パソコンを使って金額を確認するため、基本的な入力操作もできると安心です。
問診票(もんしんひょう)
初めて来院した患者さんに、今の体調や症状、持病などを記入してもらう用紙です。これをもとに医師が診察を進めます。
問診票を渡して「ご記入ください」と声をかけるのも受付やクラークの大事なお仕事。記入漏れがないか確認するのも忘れずに行います。
カルテ
カルテとは、医師が患者さんの診察内容や治療経過を記録するためのノートやデータのことです。最近はパソコンで管理する「電子カルテ」が主流になってきています。
クラークは、カルテの準備や、診察前に内容を確認するサポートも行います。医師の近くで働くことが多いので、診療の流れを理解しておくことが役立ちます。
処方箋(しょほうせん)
お医者さんが「この薬を出します」という内容を記載した用紙で、患者さんはこれを持って薬局に行きます。
クラークは、処方箋がきちんと印刷されているか、患者さんに渡し忘れていないかを確認する役割を担うこともあります。
初診・再診(しょしん・さいしん)
「初診」はその医療機関に初めてかかったとき、「再診」は2回目以降の受診を指します。診療報酬(病院が保険から受け取るお金)の計算にも関わる重要な区分です。
受付では、患者さんが「初診」か「再診」かを見極めて正しく対応することが求められます。
自費診療(じひしんりょう)
健康保険が使えない診療のことです。たとえば、美容注射や健康診断などが自費にあたります。
保険証の提示があっても、内容によっては自費になる場合もあるので、説明の仕方や案内にも注意が必要です。
レセコン
「レセプトコンピュータ」の略で、医療費の請求書を作成する専用ソフトのことです。保険診療では、診察内容を点数にして保険者に請求します。
慣れるまでは操作がむずかしく感じるかもしれませんが、多くの職場ではマニュアルがあり、徐々に使い方を覚えていけます。
クラーク
クラークとは、医師や看護師のサポートをする事務スタッフのことです。外来クラーク、病棟クラークなど配属先によって仕事内容が異なります。
たとえば外来ではカルテの準備や患者呼び出し、病棟では入退院手続きの補助や診断書の管理などを担当します。医療現場を支える大切な存在です。
よくある質問(Q&A形式)
Q:全部覚えておかないとダメ?
→ いいえ、働きながら少しずつ覚えれば大丈夫です。現場では実際の流れの中で覚えていくことが多いので、最初から完璧でなくてOKです。
Q:難しい用語が出てきたらどうする?
→ 先輩やマニュアルに聞いたり、都度メモしておくのがコツです。「わからないことは聞いてもいい」という気持ちで取り組むことが、成長につながります。
まとめ
医療の現場では、はじめて聞く言葉も多いですが、焦らなくても大丈夫です。今回ご紹介した10の用語をなんとなくでも知っておくだけで、実際に働き始めたときの安心感が違います。
これから医療しごとにチャレンジしたい方は、ぜひこの記事をきっかけに、少しずつ知識を深めていってくださいね。
初心者向けの参考教材はこちら
もっと詳しく学びたい方には、初心者向けのテキストや通信講座もおすすめです。実際に現場で役立つ知識をやさしく学べる教材を以下で紹介しています。
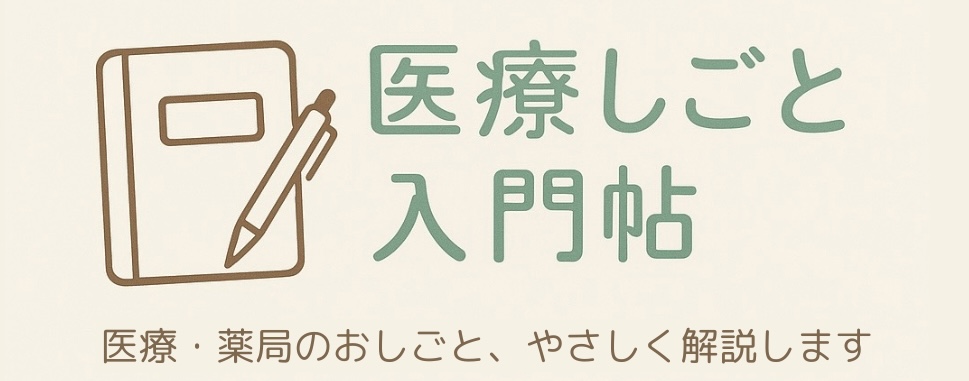
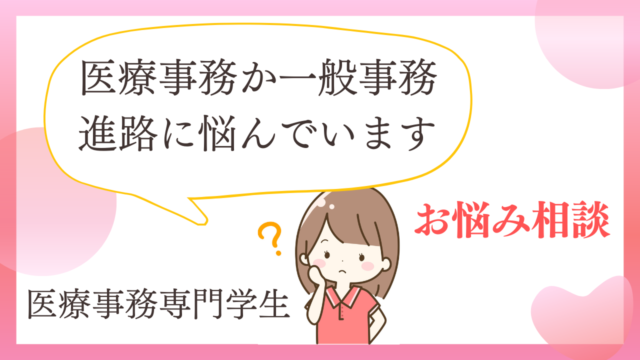
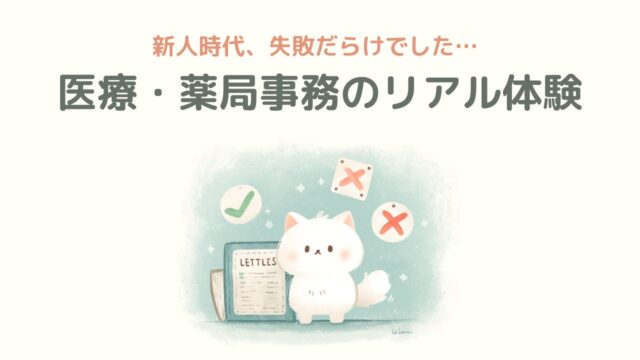


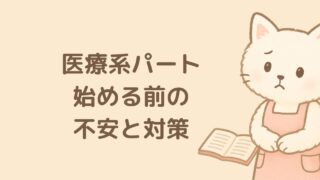

 >>>詳しくははコチラから
>>>詳しくははコチラから